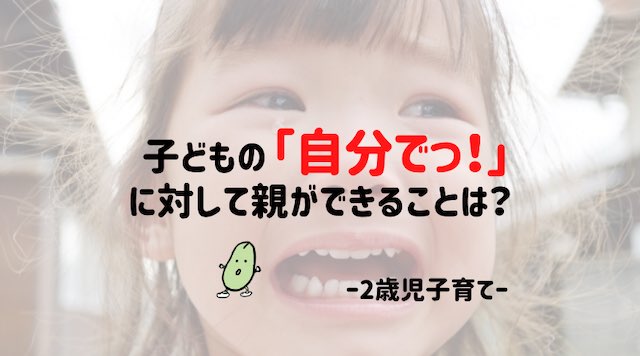
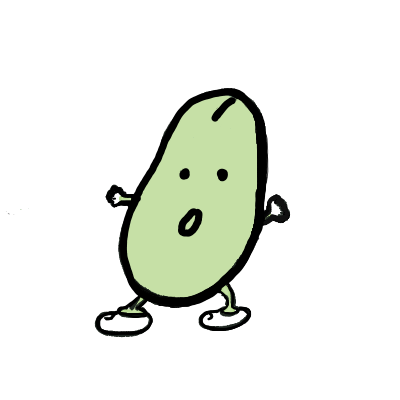
私は、現在2才の娘を育てている男性サラリーマンです。
現在、私が育児時短を取得し、保育園の送迎を行っています。
子どもは最近だんだんと自我が芽生えてきて、全てのことに対して
自分でっ!
と言って何でも自分でやりたがる時期がきています。

私も保育園の送迎時やお風呂・食事、生活の全てで「自分でっ!」と言う言葉を聞かないことの方が少ないくらいです。
そんな時、皆さんはどうしていますか??
本記事では、そんな「自分でっ!」という2才児に対する親の向き合い方を自分の経験を踏まえて記事にしました。
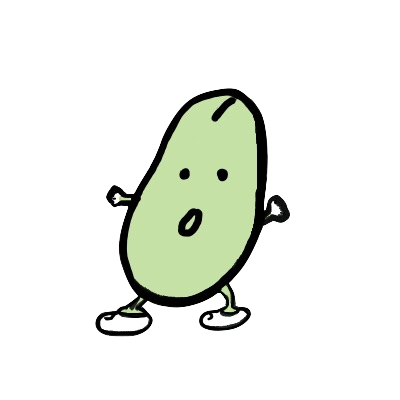
1.なぜ2才児は「自分でっ!」と言うのか?
まず、初めになぜ2才児は「自分でっ!」と言うのでしょうか。
結論から書くと、2才児の時からもう
自立への第一歩
を歩み始めているからなんです。
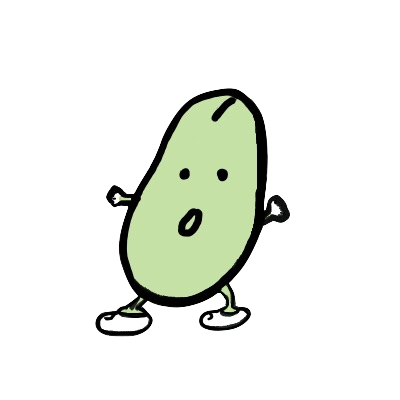

自分でっ!まめっ!
ふむふむ、チビまめも自立したがっていますね。
上記の話をより具体的に言うと、
自分の随意筋(ずいいきん)を思い通りに使えるようになりたいから。
ということなんです。
随意筋とは手や足、顔などの自分の意思で動かせる筋肉のことです。
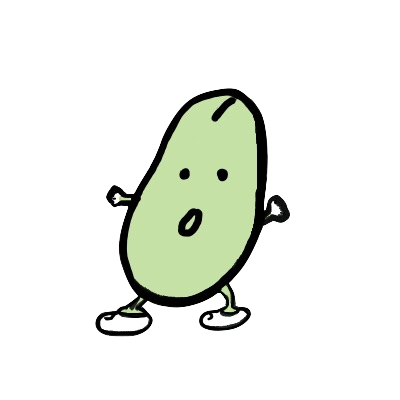

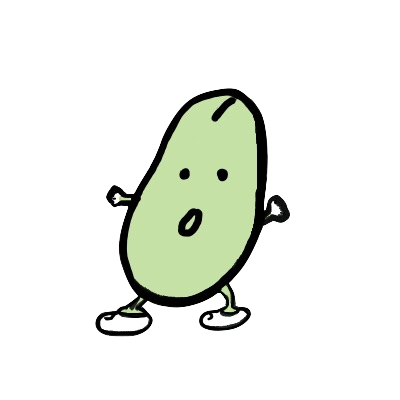
「おい!おれの筋肉」を知っているまめとは…
まだまだ動き始めたばかりの小さいうちは筋肉1つ動かすこともままならない状態です。
でも、大人と同じように自分ひとりで動きたい。
親はこの気持ちをしっかりと汲み取ってあげる必要があります。
「出来ないのに何でやりたがるの」「何でこんなことできないの」という親の気持ちが、この時期の子どもと親が衝突してしまう主な理由です。
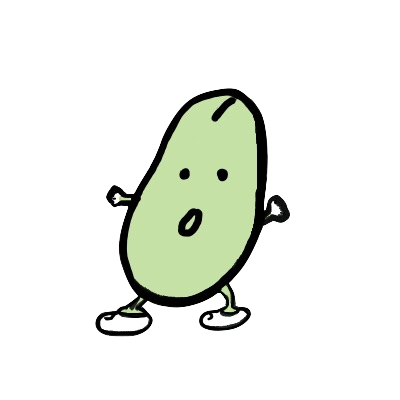
あわせて読みたい(参考にした本)
2.「自分でっ!」と言う2才児に対して親ができることは?
次に、「自分でっ!」と言う2才児に対して親ができることは何でしょうか?
私の体験も踏まえて、以下に3つ記載しました。
2才児に対して親ができること
- 子どもの気持ちを大切にする
- 行動で教える
- 時間に余裕を持つ
それでは、それぞれ簡単に説明をしていきます。
1.子どもの気持ちを大切にする
まず、初めは子どもの気持ちを汲み取り、その気持ちを大切にしてください。
「ひとりでできるようになりたい。」という子どもの自立心を大切にすることで、将来的な子どもの大きな成長に繋がります。
私は、子どもが「自分でっ!」と言ったら、少しだけ離れてみて子どもを見守るようにしています。

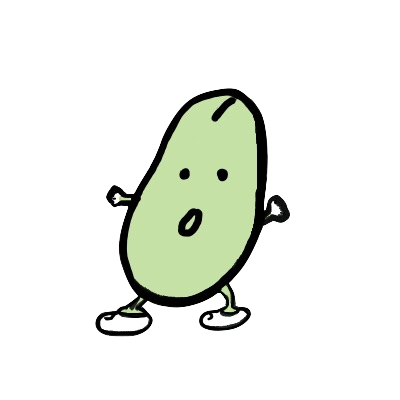

2.行動で教える
次に、実際の親の行動で教えることが大切です。
子どもは「自分でっ!」というものの、できないことばかりです。
しばらくはそーっと見守ってあげて、どうしてもできない時には、出来ない部分を親がお手本を見せてあげるようにしてください。
そうすることで、できないことが少しずつできるようになっていきます。
以下に、「して見せる技術」の手順を記載します。
〔して見せる技術〕
①して見せるとき、言葉を添えないで黙ってする
②子どもがやりたがっている活動を、ひとつだけ取り出す
③動作を分析し、順序立てる
④できるだけ動きをゆっくりにして、はっきり、順序立てて見せるママ、ひとりでするのを手伝ってね!より
お手本を見せる時には言葉を添えずに、動きだけで示す方法が有効です。
引用先の本でも、お手本を見せる時に言葉と行動で説明をしがちですが、小さい時は目と耳のどちらか片方にに集中する方が理解しやすいと記載されています。

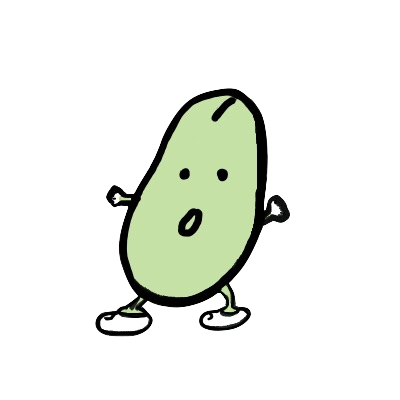
こうまめよっ!

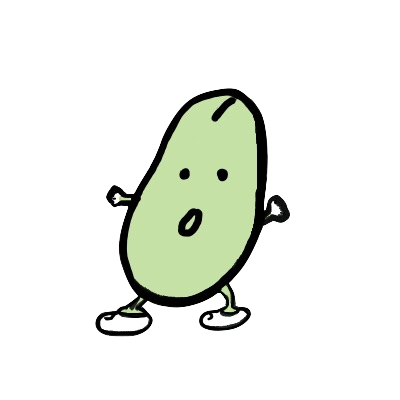
おとうさんも嬉しいまめよ!
3.時間に余裕を持つ
最後に、時間に余裕を持った行動を取る大切です。
子どもの「自分でっ!」の気持ちを尊重したくても、時間に余裕がないとできないですよね。
保育園の送迎時に、保護者から「もう時間がないから行くよ!!何してるの早く!!」といって無理やり靴を履かせて手を引っ張っていく光景をよく見かけます。
気持ちはものすごくわかります。
ですが、これではせっかくの子どもの自立心を育むことはできません。
私は娘が自分で行動する時間を考慮して、初登園以降ずっと保育園に20分以上の余裕を持って送り迎えをするようにしています。
(子どものペースでゆったりしているので、園内でいつも数組の家族に追い抜かれています笑。)
育児は少しずつ前倒しで準備をし、時間にゆとりを持った育児をすることが大切です。
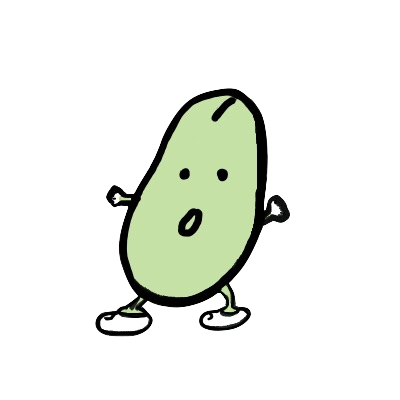
3.最後に
本記事では、「自分でっ!」という2才児に対する親の向き合い方について記事にしました。
自我が芽生え・自分でやりたい時期に突入した時には是非とも広い心で我が子の成長を見守ってあげてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
あわせて読みたい


-300x167.jpg)







-300x167.jpg)




-150x150.jpg)
-150x150.jpg)

-150x150.jpg)